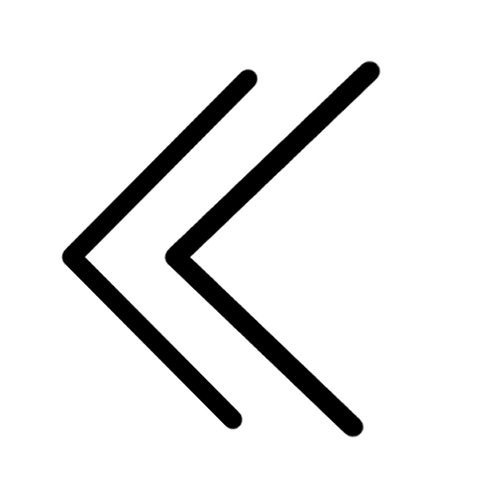野乃花前日譚 第一章その2
「ころばぬ こころは ここにない」
[はじめに]
お恥ずかしながら、前回からずいぶんと間が開いてしまったので……まずはおさらいから入ろうと思う。
当時の私――静間真澄(16)は、自分が遭うはずだった交通事故を、あろうことか実の妹に庇われてしまった、情けない高校二年生。
身代わりとなった妹――静間萌(15)は車いすに乗るようになったが、姉である私に対して、まるでなんともなかったかのように、明るく振る舞っていた。
しかしその態度が、人に傷つけられた際の萌特有の行動であることを知っていた私は、いっそう罪悪感を募らせる。
からっぽの一日を終え、孤独の帰路につく私。「一人なら傷つかないし、傷つけることもない」と、つかの間の安息を得た矢先――私は未来の新棚学園生徒会長、舞沢野乃花と出会う。
なぜか妹の車いすを押している、舞沢野乃花に。
[2-1 出会いの顛末]
続きを語るにあたって、一つ補足すべきことがある。当時の私の目には、”舞沢野乃花”という人物がどのように映っていたのか、という点だ。
彼女の表面的な人物像――つまり、見た目とか態度とか――を振り返ってみると、当時と今とで大して変わっていなかった。
特に見た目に関しては同じと言ってしまって構わない程だった。あえて違う点を挙げるとするなら、まだ制服のオーダーメイドをしておらず、デザインが平凡であったということくらいで、腰まで降りたポニーテールと肩に掛かった三つ編みのセットという、どう見ても手入れが大変そうな髪型や、凜々しさと温和さを併せ持った眼差し。これらは当時から完成されていた。
何かしらの特別な雰囲気は、一目見たときに感じていた。
しかし私は、「舞沢野乃花」を知らなかった。
目の前で妹の車いすを押している少女が、舞沢グループの社長令嬢であるとか、ましてや未来の生徒会長たる器を持った人物であるといったことなど、微塵も認知していなかったし、想像もしていなかったのである。
だから彼女に対して、特段これといった興味を持ってはいなかった。
明るくて話しやすい萌のことだから、きっと私が認知していない友達が大勢いるんだろう。その中の一人が、親切心が強いとか、たまたま帰り道が同じだったとかそういう理由で、萌の車いすを押してあげているのだろう。
その程度の、随分とあっさりした第一印象を、未来のカリスマに対して抱いていたのだった。
妥当な思考だったと思う。
結果から見れば迂闊ではあったけれど、それも仕方ない。
目の前に広がる、帰り道の住宅街。その中央に、当時の私が一番会いたくなかった人物――つまり、舞沢野乃花よりも意識すべき存在――が、ちょこんと座っているのだから。
【萌】
「……これはこれは、奇遇ってやつだね」
【真澄】
「………」
そうだね、奇遇だね。
不遇でもあるけどね。
お互いに。
本当に会いたくなかったよ。
どんな顔すればいいか分からないから。
【萌】
「………?」
固まっている私を見上げて、萌は不思議そうに首をかしげた。この姉はどうしてそんなに動揺しているのだろうか。と、状況をまるで理解できない様子だった。
【野々花】
「萌のお知り合い?」
そんな私達を見かねたのか、それとも単に気になったのかは分からないが、最初に口火を切ったのは舞沢野乃花だった。萌はこの至極真っ当な質問を受けると、はっとした表情を浮かべて、
【萌】
「……ああ〜、そっか。そういえばお姉ちゃん、野々花ちゃんと会ったことなかったね。人見知りで緊張しちゃってるんだ」
と、見当違いな早合点をしてくれた。私としても、そのように誤解されていた方が場が持ちそうなので、願ったり叶ったりだった。
【野々花】
「お姉さん……ということは、真澄さん? 前に話してた」
【萌】
「あ、そう。流石野乃花ちゃん。一度聞いたことは忘れないね~」
【野々花】
「褒めたってなにも出ないわよ」
舞沢野乃花は萌の賞賛を聞き飽きたように流しつつ、「手、離すわよ?」と、萌に車いすのブレーキをロックするよう促した。萌が動作を完了したことを確認すると、彼女はこちらに向き直って。
【野々花】
「はじめまして。1年の舞沢野乃花と申します。萌とは同じクラスで、いつもお世話になっています」
柔和な笑みと共にそう言って、軽く会釈した。
こういった場における舞沢野乃花の表面的なイメージは、当時と今とで大して変わっていない。
歳不相応に丁寧な挨拶も、当然のように身につけていた。
【真澄】
「あっ、えっ、っと……」
ガッツリ動揺していた。
後輩に挨拶されたとは思えない、なんとも情けない狼狽えっぷりであった。
今も昔も、社交的な場における舞沢野乃花は、「大人びすぎている」と思う。
ただの妹の友人Aとして見ていた存在が、いきなりこんな畏まった態度をするもんだから、私としては身体が強張ること必死であった。
【真澄】
「し、しずま、ますみ……です。こ、こちらこそ妹が、お世話になってます」
【野々花】
「よろしくお願いします」
【真澄】
「よ、よろしく……」
どちらが先輩なのかよく分からないやり取りを終え、私達は再び歩き始めた。この日の彼女との会話には、まるで担任との二者面談で、冒頭に「最近どう?」と聞かれている時のような、微妙な緊張感があった。
【萌】
「野乃花ちゃんには本当にお世話になってるよ。勉強教えてもらったり、こうして車いすを押してもらったりね」
できた友人で羨ましい限りだと思ったところで、ふと疑問が浮かんだ。それは本来、萌と鉢合わせたときに真っ先に思い浮かぶべき疑問だった。
【真澄】
「……帰りは、徒歩? だったんだ。行きは車だったのに」
【萌】
「……まあ、うん。そんな感じ」
【真澄】
「……そっか」
含みのある返事だったが、これ以上の追求はできなかった。登下校にまつわる事柄は萌と母親の間だけで話が済んでおり、私が口出しする余地はなかった。二人が私をのけ者にしたのではない。私が目を逸らし、耳を塞いだのだ。
そういった後ろめたさもあり、この件は終わりにしようと思っていたところで、舞沢野乃花が口を開いた。
【野々花】
「元々、お母様に車で迎えに来てもらう予定だったんですが、昼休みになったときに、萌が車いすで下校したいと言い出したんです」
【萌】
「あっ、もう、せっかくぼかしたのに」
【野々花】
「家族相手に誤魔化しても、どうせ後でバレるわよ」
【萌】
「そうかもしれないけど……まあいっか」
顔を赤らめつつ、諦めの溜息をついた萌は、まるでトリックを見破られた犯人役のように饒舌に、これまでの経緯を話した。
曰く、元々は行きと同じ母親の車で下校するはずだったけれど、久しぶりの学校生活を送る中で、なるべく以前のような生活スタイルを貫きたいと思ったらしい。
【萌】
「車の方が楽だけど、それに慣れちゃったらいけない気がしたんだ。また歩けるようになったとき、大変そうだし」
【野々花】
「確かに、徒歩通学が不便に感じるようになるかもしれないわね。車に慣れてると」
【萌】
「野乃花ちゃんはいつも車でしょうに……」
【野々花】
「そ。だから今とっても不便」
【萌】
「えっ……なんかごめん」
【野々花】
「冗談よ。不要なところで謝らないで。萌の介助はアタシが志願したんだから」
【真澄】
「……志願?」
【野々花】
「お節介焼きなんですよ、アタシ。萌は自力で帰るつもりだったみたいだけれど、あまり一人で外出した経験がなさそうだったから、介助させてくれって頼んだんです」
【真澄】
「……なるほど」
実のところ、萌がどれくらい自走に慣れているのかどうか、当時の私には判断が付かなかった。今朝は母親の介助を大いに受けながら食事をとっていたが、あれは家の中だったからかもしれない。
【萌】
「いやー、もう大助かりだったね。今まで通ってた道ってこんなに段差あったんだ、ってなってさ。一人じゃゼッタイ苦労してたよ~」
【野々花】
「なるべく平坦な道になるよう、ルートを変えたりもしたわね。萌が方向音痴だったせいで、かなり遠回りをしたけれど」
【萌】
「そうそう、おかげでお姉ちゃんとバッタリってわけ」
以前は同じ通学路を歩いていたのだから、”鉢合わせる” には何らかの変化がないといけなかったことに今更気付いた。当時の私がどれだけ頭が回っていなかったかがよく分かる。
【真澄】
「それは……その、妹がご迷惑をおかけしました……」
【野々花】
「いえいえ。迷惑だなんてとんでもない。立派だと感心するばかりです」
さらりと流して、すかさず妹を褒める舞沢野乃花。この辺りの立ち回りはやはり歳不相応というか、場慣れしすぎている。(年上に敬語を使われているのも慣れているのか、何も言ってこなかったし)
【野々花】
「不幸が降りかかってきても、めげずに前を向く姿勢。アタシも見習いたいし、そういう人の手伝いがしたいです」
【真澄】
「…………」
人の良い点を躊躇なく言語化する。それが舞沢野乃花の性格で、私が彼女を好きな理由の一つでもあるけれど、当時の私にしてみれば、妹を持ち上げる彼女の言葉は、なんとも複雑な気分になるものであった。
そうです。
萌は立派な妹なんです。
苦しいことがあっても、明るく振る舞って、いつの間にか立ち直っているような、本当にできた妹なんです。
【萌】
「不幸じゃないよ、野乃花ちゃん」
【萌】
「萌が自分で飛び出しただけなんだから、自業自得だよ」
こうやって、笑って、加害者を見ないように、「居ないように」して、気持ちに折り合いをつける子なんです。
そうやって、無理をする子なんです。
【真澄】「ちがう」
【真澄】「わたしのせいだ」
【真澄】
「……ごめんなさい」
言えるわけがなかった。
こんな姿を見せられたら、萌の無理を邪魔するような言葉なんて、何一つ発せられなかった。
萌はこのまま、一人で立ち直っていく。そうあるべきだ。そこに私が介入する余地はないし、あるべきではない。
萌には会いたくなかった。どんな顔をすればいいか分からなかったから。
でも案外、会えて良かったかも知れない。これから自分がどうすればいいか、見えてきたような気がする。
私は萌の近くにいるべきではないんだ。
ましてや、人前で謝るなんてことをしてはいけないんだ。
そんなことをしたら、萌の生き方を否定してしまうから。
そっと距離を置くこと。それこそが、静間萌の加害者として正しい在り方なんだ。
でも、どうしよう。
耐えられそうにないよ、私。
この胸に渦巻く罪悪感を、抱え続けなきゃいけないなんて。
【真澄】
「……萌、私……」
先に帰る。と言おうとしたところで、私は異変に気が付いた。
【野々花】
「………」
さっきから、ずっと。
私のことを見つめていた。
萌ではなく、私のことを。
哀れむような。
慈しむような。
とても優しい視線だった。
その優しさが理解できなくて。
理解できないことが怖くて。
もうぜんぶわからなくなって。
私はその場から逃げ出した。
【萌】
「えっ、お姉ちゃん!?」
【野々花】
「あっ……」
あのときの舞沢野乃花には、私がどのように映っていたのだろう。
当時の私は何も話していなかったのに、まるで全てを見透かされたかのような気分になった。その上で、自分の理解を超えた優しさを向けられているような気がして、それがとても不気味だった。
今になって思い返してみれば、思い込みも甚だしい。
けれど、思い込みが必ずしも思い過ごしになるとは限らないのだ。
この件の答え合わせは、もう少し先の話になる。ただ、読者諸君にはどうか安心して欲しい。
だってこれは、私が舞沢野乃花に救われる物語なんだから。
あの瞬間、私の中で舞沢野乃花という少女は特別な人間として記憶に刻まれることになった。
お世辞にも良い初対面ではなかったけれど。
大事な思い出であることは、疑いようがない。
[2-2 ひとりよがりなひとりごと]
さて、萌より早く家に帰った私は、すぐに私服に着替えて外出した。
親には「友達と遊びに行ってくる」と嘘の連絡を入れて、ひとり街中を歩いたり、カフェでぼーっとカフェオレを飲んだりして、ただ日が暮れるのを待った。
九時頃に帰って、一人で冷めた夕飯を食べた。
お風呂に入るタイミングで、飲み物を取りに来た萌とすれ違った。
何も会話はなかった。
その後は自室に籠もって、ただぼーっとしていた。
そうして深夜を待った。
玄関がノックされるのを待っていた。
こんこん、と。
待ち望んでいた音が鳴ったときは、思わず胸が躍った。
【つばき】
「ずいぶんと浮かない顔してるじゃん、真澄」
【真澄】
「……まあね」
話して何かが変わるなんて、本当は期待しちゃいけない。
それでも、縋らずにはいられなかった。
私の唯一の悪友に。
その結果は、また次回(今度こそ来月)にお話しするとしよう。
今月はここらへんで。
それではまた。